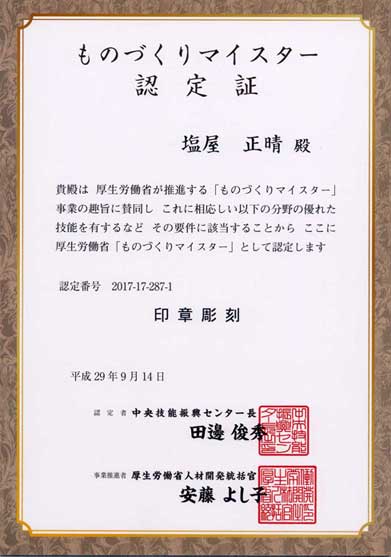
石川県職業協力開発協会の要請で2017年から県内(主に金沢市)の小学校に「篆刻の指導」に伺っています。
作業に取り掛かる前に一連の手順を説明させていただき中国産の柔らかな石を用い生徒さんに鉄筆(てっぴつ:篆刻用の彫刻刀)で彫っていただいています。自分の名前の一文字(漢字・ひらがな・カタカナ)様々ですが、殆どの生徒さんが初めてとは思えないほど手際よく彫刻される事にいつも感心するばかりです。 完成したハンコの印影を見ている生徒さんの目はみんな輝いています。

2017年12月 金沢市立兼六小学校 |

2019年2月 津幡町立中条小学校 |

2019年10月 川北町立中島小学校 |

2019年11月 金沢市立小坂小学校 |

2020年2月 津幡町立中条小学校 |

2020年10月 白山市立蕪城小学校 |

2020年10月 金沢市立中村町小学校 |
06-300x225.jpg)
2020年11月 金沢市立伏見台小学校 |

2020年11月 白山市立朝日小学校 |
|
2020年12月 金沢市立中央小学校 |
2021年1月 野々市市立館野小学校 |
-300x225.jpg)
2021年2月 津幡町立英田小学校 |
|
2021年11月 金沢市立中央小学校 |
2021年11月 野々市市立館野小学校 |

2022年2月 能美市立寺井小学校 |
|
2023年6月 川北町立中島小学校 |
2023年7月 加賀市立三谷小学校 |

2023年11月 かほく市立金津小学校 |
|
2023年6月 金沢市立花園小学校 |
2023年7月 金沢市立中央小学校 |

2023年12月 野々市市立館野小学校 |
それって本当に手彫りの印鑑ですか? テキスト表示するなら誰でもできます
ネットでは,当たり前のように「手彫り印鑑」の記載表示が氾濫しています。 あなたも不思議に思った事はございませんか?
ありえない価格と速さ・・・本当にそれは人の手で彫ったハンコかどうか買う立場になると困惑するのは当然です。
注文してお手元に届いたものが、ロボットで誰でもできるとしたら残念だとは思いませんか・・・?
ご安心ください、私は手彫りの証拠を完成した印鑑にお付けすることができます。
手彫り印鑑・塩屋印房 https://www.shioya-inbo.com/








